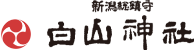地鎮祭(じちんさい)とは
家(建物)を建てる前に、土地(大地(だいち))の神様とその地域をお守りくださっている神様をお招きして、土地をはらい清めて、これから行われる工事の安全とご家族の皆様の安全をお祈りするおまつりが地鎮祭であります。
地鎮祭のおまつりの内容は、 まず、皆様をおはらいして清めまして、神様が宿られる榊に神様をお招きしてお供え物を捧げます。 次に神職が、この土地に家を建てることを神様にご報告し、災いが無く、無事に家が完成することをお祈りする祝詞を奏上します。

続いて、この土地全体をお清めする切麻散米を行い、 その後に地鎮行事を執り行います。地鎮行事とは、土地の神様を鎮める儀式であり、鍬入れの儀とも言われています。現在では、機械を使って土地を平らに均していますが、昔は手付かずの土地を鎌で草を刈って、鍬で土を掘り起こして、鋤で土を平らに均したとされています。家を建てるに当たり、荒れた土地に人間が手を加える様子を神様にご覧戴き、建築の許可を得るという意味もあります。
また、土地の神様をお鎮めするために納める鎮め物を土の中に埋めてお供えする場合もあります。 鎮め物の内容といたしましては、人・楯・鉾・刀などを型取ったものを鎮め物として、それらを敷地中央の土の中に埋めて、土地の神様をお鎮めすると共に、これから建築する新しい家に災いが降りかかること無く、末永く丈夫で、ご家族の皆様が安心して住む家として、この地に定まることをお祈りするものであります。
続きまして、施主様をはじめ、ご関係の皆様より玉串を捧げておまいりをして戴きます。何事もなく、無事に家が完成するよう、また、家族が健康で災いなく代々、末永く住む事ができるようなど祈願して戴きます。
最後に、今日お招きしました神様にお帰り戴いて地鎮祭は終了となります。

祝詞奏上
(のりとそうじょう)
切麻散米
(きりぬささんまい)
地鎮の儀
(じちんのぎ)
鎮物埋納
(しずめものまいのう)
お申込み手順
予めお電話等で1週間前まで
にお申込み下さい。
細かな打合せが必要な場合は、来社戴く場合があります。
- ※神社で神事などがある場合には、日時の変更をお願いすることもございますので、ご了承願います。
- ※1月11月中はお受けできない時間がありますのでご了承願います。
不動産業者様、建設業者様、工務店様と話を進めて土地、新築が決まりましたら「地鎮祭を行う」との意向をはっきり伝えてください。地鎮祭も一つの宗教活動になるので地鎮祭の話を持ち掛けない会社もあるようです。日程など話がまとまりましたら、当神社へお問合せ下さい。連絡は慣れている業者様から連絡してもらえた方が安心です。もちろん施主様ご自身からでも構いません。
建替えの場合でも通常は地鎮祭を行います。「建替えであれば必要ない」という所もあるかもしれませんが、新潟では増築、改築、取壊し等でもおはらいを行います。
業者様でいつもお願いしている神社があるかもしれないので、重ならないようにご注意下さい。
式次第
- 一、開式
- 一、修祓(しゅばつ)
- 一同起立・低頭
- 一、降神(こうじん)
- 一同起立・低頭
- 一、献饌(けんせん)
- 一、祝詞奏上(のりとそうじょう)
- 一同起立・低頭
- 一、切麻散米(きりぬささんまい)
- 一、地鎮の儀(じちんのぎ)
- ・苅初めの儀(かりそめのぎ)
- 鎌入れ
- ・穿初めの儀(うがちぞめのぎ)
- 鍬入れ
鋤入れ - ・鎮物埋納(しずめものまいのう)
- 一、玉串拝礼(たまぐしはいれい)
- 一、撤饌(てっせん)
- 一、昇神(しょうじん)
- 一同起立・低頭
- 一、閉式
- 一、神酒配戴(しんしゅはいたい)
ご用意戴くもの
(祈願主様でご用意戴く場合の一例)
初穂料2万円の場合
祈願主様でご用意戴く場合の準備品になります。
- お米(白米を皿に軽く山になるようにご準備ください)
- 清酒(1升瓶または4合瓶 銘柄に決まりはありません)
- 海の物(例:魚または、昆布、海苔、スルメ、寒天等)
- 野菜(例:大根、人参、きゅうり、とまと、なす等 数種類を数個)
- 果物(例:りんご3個、みかん5個、バナナ一房等 一種類を数個)
- 塩1盛 (小皿に軽く山になるように準備ください)
- 水 コップ1杯
上記のお供え物とその皿、テーブルをご準備ください。海の物、野菜、果物はお供え物の個数に決まりはありません。
また、送迎用の車輛(タクシーでも構いません)のご用意をお願い致します。
初穂料3万円の場合
- 清酒(1升瓶または4合瓶 銘柄に決まりはありません)
- 水 (水道水、ペットボトル500mlなど) 水器(入れ物)はこちらで用意致します。
- 送迎用の車輛(タクシーでも構いません) 祭具を積むのでトランクを空け来社ください。
地鎮祭等屋外での祭典の場合
- 屋外で斎竹が必要な場合は4本
- テント(屋外の祭典で雨天の場合)
- 盛砂(地鎮の儀を行う場合)
地鎮の儀の祭具(鎌、鍬、鋤)、鎮物は当社で準備することができます。
※積雪のある場合は祭典場所の地面が見えるようにしてください。
※個人でお申し込みの方は、施工業者様にご相談ください。
式の流れ
1. 修祓(しゅばつ)
おはらいをして清めます。
2. 降神の儀(こうじんのぎ)
この地(神籬)に神様をお招き致します。
3. 献饌(けんせん)
神様にお供え物を致します。

4. 祝詞奏上(のりとそうじょう)
工事の安全とご家族の皆様の繁栄、安全をお祈り致します。

5. 切麻散米(きりぬささんまい)
敷地の四隅に切麻を撒き、災いがないように敷地をはらい清めます。
米麻散米(こめぬささんまい)また四方祓(しほうはらえ)ともいいます。

6. 地鎮の儀(じちんのぎ)
- ・苅初めの儀(かりそめのぎ)
鎌入れ(かまいれ)…設計者さま
盛砂に生える草を鎌で刈る神事です。本来は童女が行う神事ですが、慣例で建物の設計者に担当して戴きます。省略されることもあります。

- ・穿初めの儀(うがちぞめのぎ)
鍬入れ(くわいれ)…施主さま
鋤入れ(すきいれ)…施工・工務店さま
盛砂に忌鍬(いみくわ)忌鋤(いみすき)で穴を掘る神事です。慣例で忌鍬を施主さま、忌鋤を工務店さまに担当して戴きます。
昔は手付かずの土地を鎌で草を刈って、鍬で土を掘り起こして、鋤で土を平らに均したことに由来しております。

- ・鎮物埋納(しずめものまいのう)
鎮物(しずめもの)を埋め納めます。

7. 玉串拝礼(たまぐしはいれい)
玉串を捧げておまいりをして戴きます。玉串拝礼はまず神主が行い、続いて施主さま、ご家族さま、工務店さまに行なって戴きます。ここで神籬に宿る神様に直接おまいりし、工事の安全とご家族の皆様の繁栄、安全をお祈り下さい。
8. 撤饌(てっせん)
神様にお供えした神饌(しんせん)を下げます。
9. 昇神(しょうじん)
神籬にお招きした神様にお戻り戴きます。
10. 神酒拝戴(しんしゅはいたい)
神様にお供えした御神酒で乾杯します。

お申込み方法
予めお電話等で1週間前まで
にお申込み下さい。
細かな打合せが必要な場合は、来社戴く場合があります。
- ※神社で神事などがある場合には、日時の変更をお願いすることもございますので、ご了承願います。
- ※1月11月中はお受けできない時間がありますのでご了承願います。